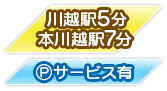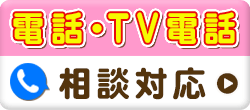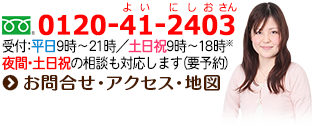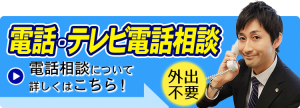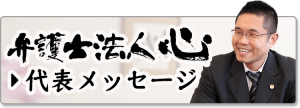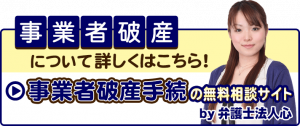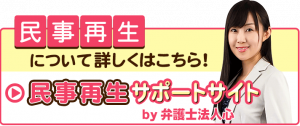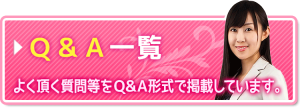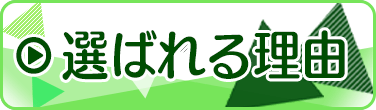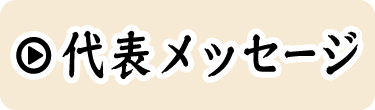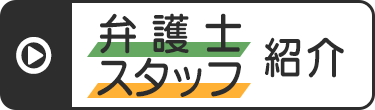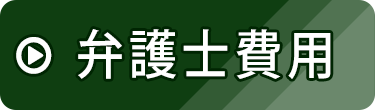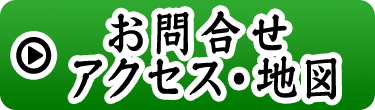合同会社の破産手続き
合同会社は株式会社と異なり、取締役や株主総会が不要で、利益の分配率を任意に決定できるなど、自由度の高い組織設計ができる法人です。
株式会社と比べ、低コストで設立できることもメリットであるといえます。
一方、株式会社に比べると社会的な認知度や信用度は高くなく、融資を受けにくいケースもあり、資金繰りが難航するということも考えられます。
本記事では、合同会社の倒産に関する事項を説明していきます。
1 合同会社の経営が厳しい場合にとれる倒産方法
合同会社が選択することができる法的な倒産の方法は、「法人破産」または「民事再生」です。
法的な倒産の種類には他に「特別清算」と「会社更生」がありますが、これらは株式会社でないと利用できません。
では、法人破産と民事再生とはどのようなものなのでしょうか?
⑴ 法人破産
法人破産は、裁判所に申立てを行い、会社の法人格と債務を消滅させる手続きです。
一般的な倒産のイメージに最も近い方法かもしれません。
破産手続きにおいて、会社の財産はすべて換金され、債権者への弁済に使われます。
会社を清算し、法人格が消滅するので、清算型の倒産と言われます。
なお、代表社員(株式会社の代表取締役に相当)が会社の保証などをしている場合、滞納した税金などは消滅せず、代表社員に支払義務が生じます。
⑵ 民事再生
民事再生も裁判所を介した債務整理の手続きですが、破産とは異なり債務を減額し、事業を継続することができます。
このことから、再建型の倒産と言われます。
ただし民事再生をするためには、減額後の債務を問題なく返済できる見込みがあることを、裁判所に認めてもらわなければなりません。
また、手続中に何度か債権者の同意を得ることが必要となるため、これをクリアする必要があります。
さらに、担保のある債務は減額されないので、整理可能な債務が限定されているという点にも注意が必要です。
2 合同会社の破産の流れ
合同会社が法人破産する場合、株式会社と類似した手続きが行われます。
以下、詳しく説明します。
⑴ 弁護士への相談と法人破産の準備
自己破産の場合には「同時廃止」と、本来の手続である「管財事件」がありますが、法人破産の場合には必ず「管財事件」になります。
法人破産をすると法人の財産は処分されてお金に換えられ、債権者への弁済に充てられます。
この手続きは、裁判所が選任する「破産管財人」が実施します。
破産申立て前に財産を処分すると、問題となることもあるので、法人破産を検討する場合はまず弁護士に相談してください。
本当に法人破産をするべきなのか、そして法人破産をどのように進めれば良いのかという点について検討することができます。
弁護士に法人破産を依頼した場合には、裁判所へ申立てをするための準備を任せることができます。
⑵ 裁判所に申立て
法人破産申立てに必要な書類や資料が用意できたら、裁判所に法人破産の申立てを行います。
代表社員が裁判所へ行く必要はなく、弁護士が代理人として申立てますのでご安心ください。
⑶ 破産審尋
申立て後、裁判官と破産申立人で「破産審尋」という面談を行います。
ここには、原則として代表社員が出席する必要があります。
裁判所によっては、申立人の弁護士・裁判官・破産管財人になる予定の弁護士で面談を行うということもあります。
⑷ 破産手続開始決定
申立て時の書類や資料、破産審尋の内容などから、裁判官が問題ないと判断した場合には、破産手続きが開始されます。
破産手続開始決定は、合同会社の解散事由のひとつともされています。
⑸ 破産管財人の選任と換価処分の開始
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が正式に選任されます。
破産管財人の役割は破産手続きの実行であり、具体的には以下のようなことを行います。
・会社の財産や負債の調査
・会社の財産を売却(換価処分)
・換価処分で得たお金を債権者へ分配(配当)
破産申立人は管財人に協力する義務があるため、管財人の求めに応じて、会社の帳簿を含めた財産、負債、その他資料などを開示する必要があります。
管財人と面談が行われることもあるので、質問等に対しては誠実に回答します。
郵便物も調査の対象であり、会社宛の郵便物はすべて管財人の事務所に届くように変更されます。
管財人による確認が終了した郵便物については、定期的に返却を受けます。
申告していない財産や債権者が存在する場合、この段階で判明することもあります。
⑹ 債権者集会
管財人による調査や換価処分が進むと、裁判所で「債権者集会」が行われます。
債権者集会では、管財人が調査や換価処分の進捗を説明します。
債権者が参加しないこともあり、裁判官・裁判所書記官・管財人・破産申立人・破産申立人の弁護士しか出席しないという場合もあります。
債権者集会は、多くの場合数十分程度で終わり、紛糾することもあまりありません。
また、事案によっては債権者集会が複数回行われることもあります。
⑺ 配当
換価処分によって得られた現金を、管財人が各債権者に配当します。
⑻ 破産手続の廃止と法人の消滅
配当が終わると破産手続きが廃止(終了)されます。
3 合同会社の破産費用
合同会社の破産を行うためには、裁判所に支払う費用と、弁護士費用が必要となります。
⑴ 一般的な裁判所費用の金額
・申立手数料:1000円
・官報公告費:14786円
・予納郵券:3490円+α
・管財手続費用:20万円~
申立ての手数料、官報公告費、予納郵券代などで数万円必要となります。
会社の財産や負債の状況が比較的単純である場合には、少額管財事件となり、その場合の予納金は20万円程度です。
⑵ 特定管財の管財手続費用
債権者が多い事件や負債総額が高額な事件などは「特定管財」という扱いになります。
特定管財では管財人の負担が増えるため、管財手続費用は数十万~数百万円になります。
⑶ 弁護士費用
一般的に、合同会社の破産の弁護士費用は50万円以上が相場です。
案件の難易度によって異なるため、詳細は弁護士に確認してください。
4 合同会社の破産も弁護士へ相談を
合同会社には株式会社と違う点が多いものの、破産手続きに関してはそれほど大きな違いはありません。
まずは弁護士に相談して、何をするべきかを確認してください。
相談が早ければ、破産ではなく再建が可能な状態だと判明することもあります。
合同会社の経営が苦しくなったら、お早めに当法人の弁護士までご相談ください。